「シン、どうしたの?」
ステラがきょとんとこっちを見ている。
奇妙な浮遊感から開放されシンは我に返った。
「えっ?」
「ステラの顔に何か付いてる?」
「いやっ、何でもないよっ!」
知らない間にシンはステラの顔を凝視していたのだった。
「シン、眠いの?」
「いや、大丈夫だよ、ステラ」
顔を覗き込んでくるステラから顔を少し逸らしてシンは言った。
「ふぅん。」
ステラはまだ少し心配そうにこちらをちらちら見ている。
シンは顔が赤くなっていくのを感じた。
−なんでステラの顔を凝視しちゃったんだろ?俺の馬鹿っ!!−
「シン、あそこのベンチで休もっ。」
ステラはシンの手を引っ張って無理矢理ベンチに座らせる。
すとんと腰を下ろすと、ステラも横にぴったりと腰掛けた。
シンの心臓は早鐘のようになっていた。
「そ、そういえばステラ、香水、か、変えたよね?」
「うん、スティングがステラが欲しいって言ったら買ってくれたの。」
「へぇ。」
「ほら、これ。」
ステラは説明書をバッグから出した。
−オーブ産、高級ブランド…うわっ高っ!!なんだこれっ!!−
「いい匂いでしょ。ステラ、この匂い好き。」
「うん、いい匂いだね。」
瓶の蓋を開け深く吸い込むと、懐かしい匂いがした。
目の前に浮かぶのは懐かしい故郷の風景。
−あれは確か、マユとよく行った裏山の野原…。−
シンは香水の成分表をごそごそとめくった。
−これはっ!−
そこにはシン達が住んでいた地方ではどこにでも生えているハーブが書いてあった。
「そうか…だからか…」
「シン?」
「これ、この香水には、俺が住んでた地方によくあったハーブが含まれてるんだ。
だから、俺、これ嗅いだ時に故郷のこと思い出したんだ。」
説明書や、香水の瓶を返しながらシンは言った。
「もう、二度と戻れないけどね…」
悲しくなってシンは俯いた。
涙が零れそうだった。
シュッシュッ。
シンは首筋に冷たさを感じて驚いてステラを見た。
懐かしい香りが辺りに広がる。
「これ、シンにあげる。」
「へっ?」
「シンが持ってた方がいいから。」
「ステラ…」
ステラはにっこり笑ってシンに瓶を差し出した。
「ほんとに、いいの?だってこれ、お兄さんに買ってもらったんじゃ…」
「シンにあげるの。」
こくりとステラはうなずいた。
「あ、ありがとう。」
にこりと笑って見せるとステラは満足したように微笑んだ。
「ありがとう、ステラ。」
華奢な体を抱きしめると確かな温もりが体中に染み込んでくる。
懐かしい匂いが二人を包み込んだ。
もう二度と大切なものを失わない。
もうこの愛しい存在を二度と離したりしない。
そのために俺はもっともっと強くなろう。
ステラを守るためなら俺は鬼にもなろう。
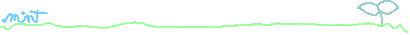

![]()